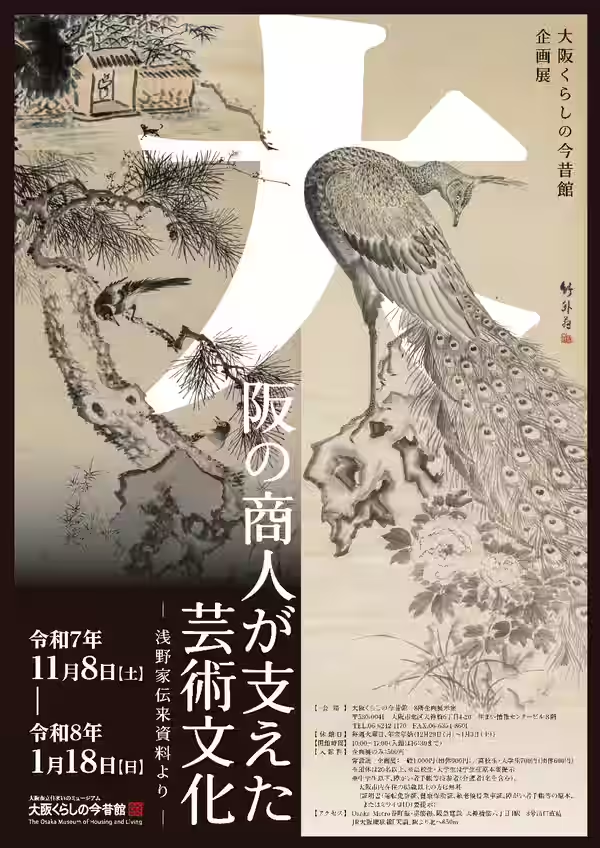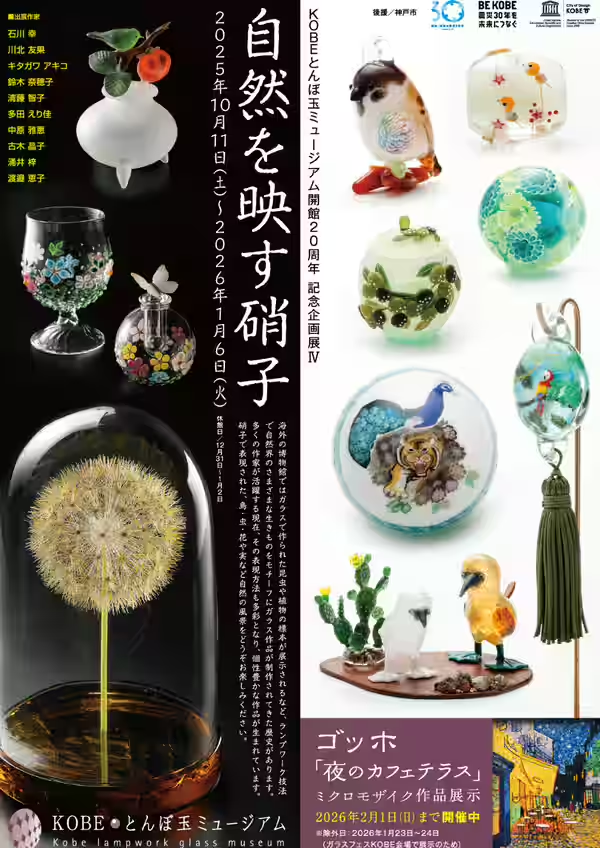山本能楽堂
日本全国能楽キャラバン!能で巡る大阪「梅」- 浪速高津宮(高津神社)
2022/12/10 (土) 人気の回
開催時刻
14:00
~
16:00
(開場 13:30)
予約締切 2022/12/10 ( 土 ) 14:00
合計予約可能人数
発生する料金
サブスクで予約可能
「予約可能な日程」に記載のあるプランに加入が必要です。
予約時に追加料金は発生しません。
コンテンツの詳細
能楽のルーツは関西にあると言われており、大阪を舞台にした演目が多数つくられ、今なお演じられ続けています。
「能で巡る大阪」公演では、能の演目に所縁のある大阪の神社関係者の方や歴史学者の方をお招きし、その神社にまつわる話や能との関りを対談形式でお話していただき、所縁のある能の演目を上演します。
今回、ご登壇頂く神社は、大阪市内でも人気が高く、地元の皆様からも愛されている神社です。しかしながら、能の舞台になっていたり、能に所縁があることはあまり知られていません。
お住いのすぐ近くや、これまでに行ったことがある、あるいは知っている歴史的な史跡を知り、学び、楽しむことで、その地域や縁のある能をさらに身近に感じていただきます。
終演後は、客席からの質疑応答にお答えします。
対談:小谷真功(高津神社)× 山本章弘
【芦刈】
前シテ(里女) 上野朝義
後シテ(梅の精) 〃
ワキ(藤原何某) 広谷和夫
ワキツレ(従者たち) 喜多雅人 矢野昌平
アイ(難波の里人) 山下守之
笛 赤井啓三
小鼓 飯田清一
大鼓 辻芳昭
後見 梅若猶義 生一知哉 大西礼久
地謡 山本章弘 波多野晋 上野雄三 吉井基晴 上野朝彦
【あらすじ】
季節は春。都の五条あたりに住む藤原何某なにがし(ワキ)は、従者(ワキツレ)を連れて難なに波わ津づ(古代の大阪湾)を訪れます。藤原は難波津の風景を見て、『万まん葉よう集しゅう』の時代の歌人、大伴家持おおとものやかもちの「桜花さくらばな今盛りなり難波の海おし照る宮に聞きこし召すなへ(桜が満開の今、難波の海に輝く宮殿におられる天皇の治世はますます栄えていく)」という和歌を口ずさみます。すると里の女(前シテ)が「どうして本当の歌を詠わないのか」と声を掛けてきました。女は、この歌に詠まれる「桜花」は実は「梅花」であると言い、そのわけを説明します。女の言葉に納得した藤原は、さらに和歌の理ことわりを聞かせるように頼みます。女は月が出る頃に現れようと言い残し、梅の木蔭に姿を消しました。
難波の里の男(アイ)が現れ、藤原に難波津の梅の由来を語り、さらなる奇特を待つように促して立ち去ります。月が難波津を照らす、ゆったりとした夜。梅の精(後シテ)が現れます。精は、梅が「うま(立派である、優れている)」が訛って「うめ」と呼ばれたこと、神代から神事・仏事や宮中の様々な行事に梅が用いられていることを語り舞い、さらにしっとりと優美な舞を見せます。やがて夜が明け初め、精は御代の久しい繁栄を寿ぐのでした。
【 浪速高津宮(高津神社)】 大阪市中央区高津1丁目1番29号
浪速の地を皇都(高津宮)と定められて大阪隆昌の基を築かれた仁徳天皇を王神と仰ぐ神社。貞観8年(899)、清和天皇の勅令によって難波高津宮の遺跡が探され、あったと定められた地に仁徳天皇を祀る社が建立されたのが始まりとされている。700年後、正親町天皇の天正11年(1583)、豊臣秀吉が大坂城を建城した際にご神体を現在地に移すが、第二次世界大戦時の大阪大空襲で神社は全焼。現在の社殿は、戦後に再建されたものである。
都合により、変更になる可能性があります。山本能楽堂ホームページでご確認ください。
山本能楽堂HP http://www.noh-theater.com/
イベント当日の流れ
未就学児の入場不可。
駐車場はございません。近隣のコインパーキングをご利用ください。
「新型コロナウイルス感染症への対応について」をご覧の上、ご来場ください。
http://www.noh-theater.com/about-covid19.html
必要な持ち物
-
マスク
出演者
上野朝義
小谷真功
山本章弘
レビュー ( 21 )
4.67
山本能楽堂 初心者も楽しめる能公演
とくい能「土蜘蛛」
2023/7/23
動きがあり、展開も早く、面白かった。
山本能楽堂 初心者のための気軽な伝統芸能入門講座
伝統芸能塾 まっちゃまちサロンPLUS <テーマ:能>
2023/7/13
笑いを交えながら、わかりやすく能楽の歴史などをお話しいただきました 能楽堂の雰囲気を感じられて良かったです 次は公演を見てみたいと思いました ありがとうございました
山本能楽堂 釈徹宗×山本章弘
能からみた日本の宗教 vol.5 「竹生島(ちくぶしま)」
2023/3/12
前々から一度は鑑賞したいと思いながらも敷居が高く二の足を踏んでおりました「能」ですが…やっと初めての機会を頂きました。 先駆けて台詞など調べ、手元に置きながらの初舞台でした。 笛や鼓の音色も、心地良いリズムも、もちろん演舞も、とても素晴らしくて本当に楽しい時間でした。 伝統的な舞台と、とても綺麗な客席、また暖かく迎えて下さった方々に感激しました。
山本能楽堂 釈徹宗×山本章弘
能からみた日本の宗教 vol.5 「竹生島(ちくぶしま)」
2023/3/12
格調高い。素晴らしい。名古屋能楽堂で、アマチュア能を見るが、レベルが違う。
山本能楽堂
釈徹宗×山本章弘 能からみた日本の宗教Vol.4「小鍛冶 黒頭」
2023/2/12
宗教の歴史や背景などのお話も分かりやすく能楽とともに楽しませていただき、とても有意義な時間となりました。 刀剣について興味を持っていたのもあり、今回の演目は特に心に刺ささりました。 小書がつかない別演出のものもいつか鑑賞したいです。
山本能楽堂
「神男女狂鬼(しんなんにょきょうき)」
2023/2/5
かつて、能が一日を通してどんなふうに展開されていたかをダイジェストで再現。その雰囲気を照明とともに体感できてよかったです。 オープニングトーク、アフタートークが初心者にももう少し分かりやすかったら…と感じました(お子さんも数名いたので)。 娯楽の少なかった当時、人々は舞台で演じられる内容からものすごく想像力を働かせて、豊かな味わいに昇華していたのでしょう。 数々の刺激に慣れた現代人が(私も含め)どこまで感性を研ぎ澄ませられるかが、楽しめるかどうかのポイントだと感じました。 それには舞台の説明や資料はかなり役立つと思います。
山本能楽堂
日本全国能楽キャラバン!能で巡る大阪「雷電」- 大阪天満宮
2023/1/29
とても良い内容でした。一緒に行った相手は能を観るのが初めてでしたが、事前事後の説明や資料等がとても充実していた事もあり、能に興味を持ってくれたようです。また機会があれば参加したいです。
山本能楽堂
日本全国能楽キャラバン!能で巡る大阪「雷電」- 大阪天満宮
2023/1/29
大変楽しかったです。 有難うございました🙇♀️
山本能楽堂
初心者のための上方伝統芸能ナイト
2023/1/14
初心者向けとわかってはいたものの、あの内容では能「花月」の話の筋も、能の魅力も伝わらない。初心者向けなのであれば、内容を解説した上で演じる等の工夫をしていただきたい。 このままのやり方でこのプログラムを続けるのであれば、二度と行かないと思います。
山本能楽堂
とくい能「田村」
2023/1/22
配布資料やMCの方による説明を通して、あらすじを頭に入れてから鑑賞することで、理解が深まりました。 逆に予備知識なしだと、そこまで入り込めなかったと思います。 アフタートークでは、伝統芸能を守る厳しさなども知ることができて、ためになりました。 敷居が高いと思われる能を、身近なイベントとして提供いただいたことに感謝です。